【整形外科で最も多い受診理由は?】
最新統計から見る患者傾向とセルフケアのポイント
こんにちは、さくら通り整形外科クリニックの宇賀治 修平です。
今回は、当院の受診統計をもとに、整形外科で最も多い症状TOP5をランキング形式で解説します。
年間4万人以上の患者さんが来院する当院ですが、腰痛、膝の痛み、肩こりなど、多くの方が共通して悩んでいる症状があります。
「なぜ痛みが出るのか」「放置するとどうなるのか」「どうすれば改善できるのか」について、最新の研究データや整形外科医の視点を交えて、分かりやすくお伝えしていきます。
1.なぜ整形外科の受診が増えているのか?

整形外科への受診が増加している背景には、いくつかの要因があります。
1. 高齢化の影響
高齢者が増えることで、膝や腰の慢性的な痛みに悩む方が増加。変形性関節症や骨粗鬆症が原因のケースが多く、転倒による骨折リスクも高まっています。
2. リモートワークの普及
コロナ禍以降、在宅勤務が定着し、多くの人が長時間座りっぱなしの生活に。
実は、「座りっぱなしの生活は喫煙よりも体に悪い」という研究データもあります。
デスクワークによる姿勢不良が、腰痛や肩こりの原因となっています。
3. スマホ・PCの影響
スマホを長時間使用することで、「ストレートネック」(スマホ首)が増加。
首や肩への負担が大きくなり、頭痛やめまいの症状を訴える方も増えています。
2.整形外科受診ランキングTOP5
ここからは、当院で最も多い受診理由TOP5をご紹介します。
それぞれの特徴、危険信号、対策方法について詳しく解説します。
第5位:骨粗鬆症
特徴
・特に50代以降の女性に多い
・骨がもろくなり、骨折のリスクが高まる
・最近は男性患者も増加傾向
危険信号
・無症状のまま進行することが多く、気づいた時には骨折しているケースも
・ウォーキングや軽い筋トレで骨を刺激する
・カルシウム、ビタミンD、タンパク質を意識した食事
・定期的な骨密度検査で早期発見
第4位:頚部痛(首の痛み・ストレートネック)
特徴
・長時間のデスクワークやスマホ使用が原因
・首の骨(頚椎)のカーブが失われることで、首や肩こりが慢性化
危険信号
・頭痛、めまい、手足のしびれが出たら要注意
対策・アドバイス
・PCモニターの高さを調整し、目線を上げる
・首や肩甲骨まわりのストレッチで筋肉をほぐす
・長時間のスマホ使用を控える(目線を上げて見る)
第3位:肩の痛み(五十肩・肩関節周囲炎)
特徴
・中高年に多いが、PC作業・スマホの影響で若い世代も増加
・肩の動きが悪くなり、痛みが徐々に強くなる
危険信号
・夜間に痛みが強くなる(特に寝返り時)
・腕を上げられなくなる(可動域制限)
対策・アドバイス
・肩周囲のストレッチ(無理のない範囲で動かす)
・軽いダンベル運動で肩の筋力を維持
・放置すると悪化するので、早めの受診が重要
第2位:膝の痛み(変形性膝関節症)
特徴
・特に40代以降の女性に多い
・膝の軟骨がすり減ることで、痛みや動きの悪さが出る
危険信号
・階段を下りる時に痛みがある
・立ち上がる時に膝がガクガクする
対策・アドバイス
・スクワットや足上げ運動で膝周りの筋力アップ
・体重管理を意識する(1kg減で膝への負担が3倍軽減)
・サポーターやインソールで膝の負担を軽減
第1位:腰痛
特徴
・整形外科受診のトップ
・ぎっくり腰、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症など、さまざまな原因がある
危険信号
・足のしびれや歩行困難がある場合は、すぐに受診を
対策・アドバイス
・1時間に1回は立ち上がってストレッチ
・腹筋や背筋を鍛えて体幹を強化
・正しい座り方を意識(腰にクッションを入れるのも有効)
↓腰痛には危険なものもあります。危険なものから身を守るためにこの動画をご参照ください↓
3.整形外科にかからないためのセルフケア
多くの整形外科疾患は、生活習慣の見直しで予防できます。ぜひ自身で取り組んで急増する痛みから自分を守りましょう!!
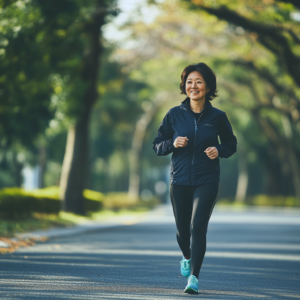
運動習慣をつける
・ウォーキングや軽い筋トレを毎日の習慣に
姿勢を意識する
・デスクワーク時の座り方、スマホを見る角度を調整
栄養をしっかりとる
・カルシウム、ビタミンD、タンパク質をバランスよく摂取
痛みが出たら早めに対処する
・違和感を感じたら放置せず、早めのケアを
☟これらの話をまとめたのがコチラ☟
まとめ
今回のランキングを見て、「もしかして…」と思う症状があった方は、早めに対策を始めましょう。
放置すると、悪化して長期間の治療が必要になることもあります。
「痛みが気になる」「この症状、放っておいて大丈夫?」と思ったら、早めに専門医に相談してください。
健康な体を守るために、日々のセルフケアを大切にしましょう。
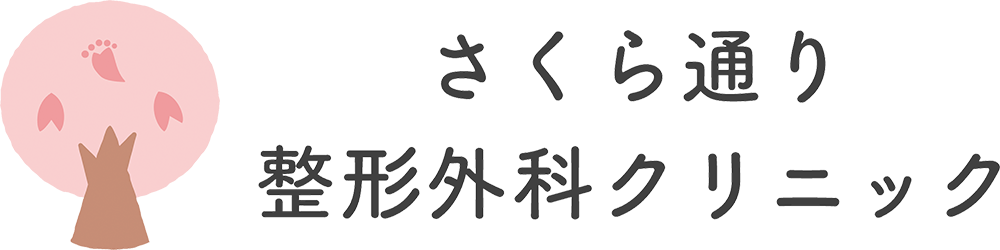

.jpeg)
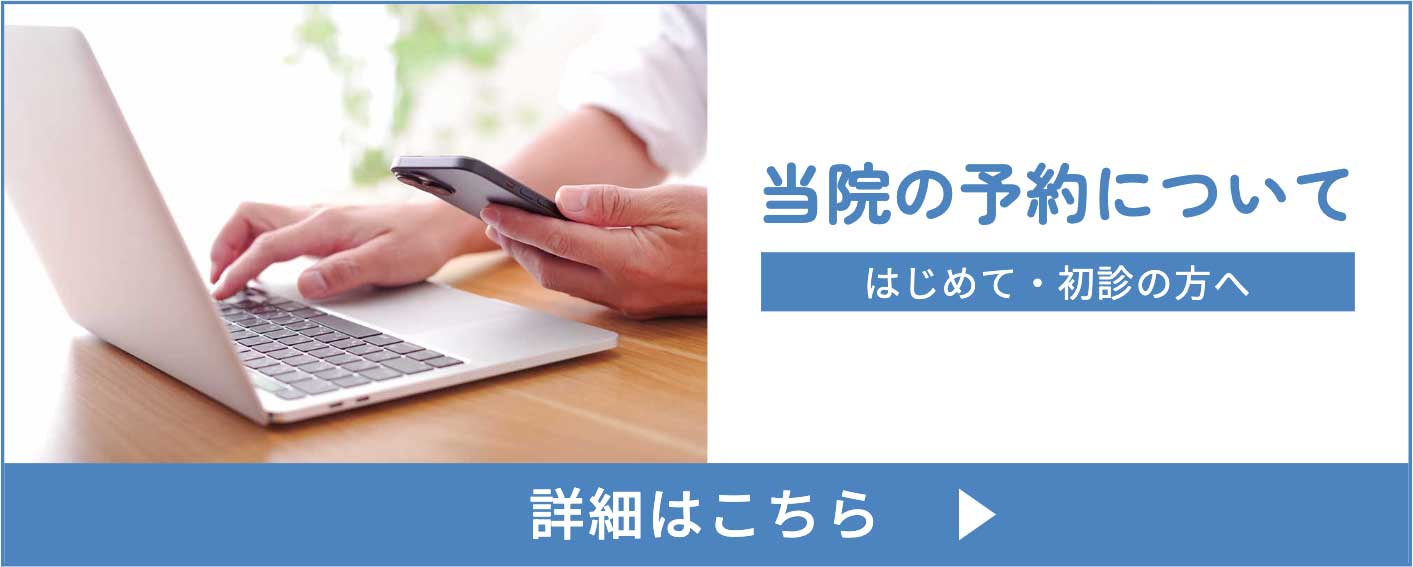
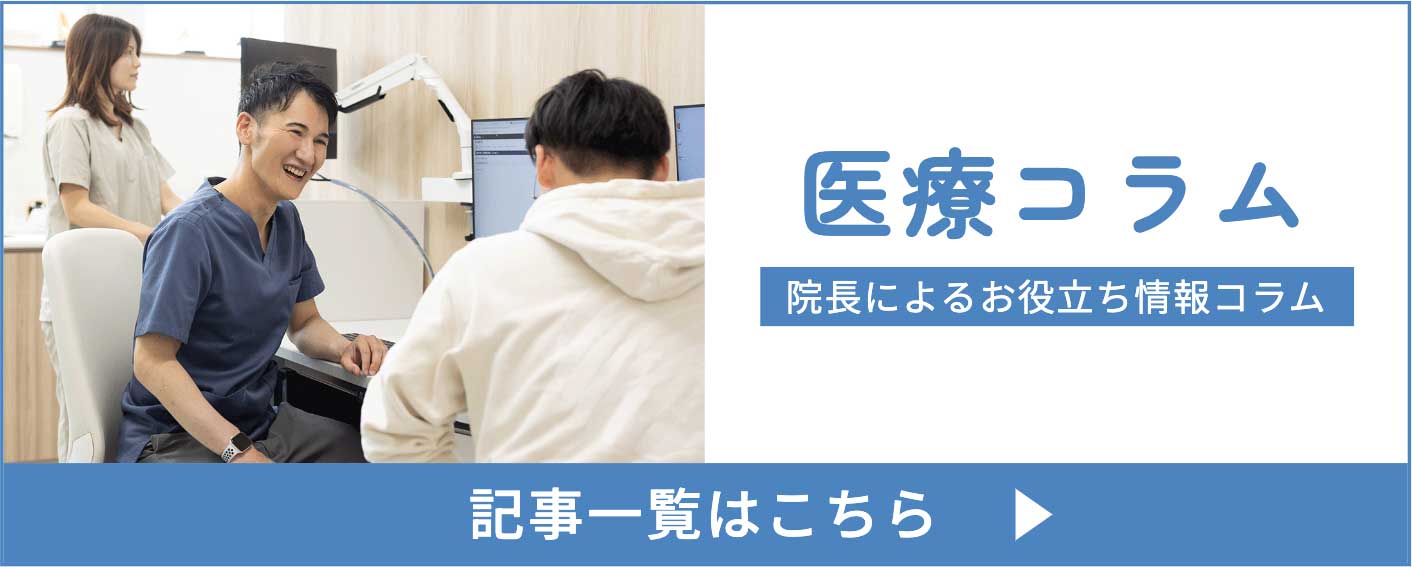



 公式Xはこちら
公式Xはこちら