膝が「ポキポキ」鳴るのは大丈夫?危険サインの見分け方と今日からできる対策

「歩いたり立ち上がると、膝からポキポキ音がするけど大丈夫かな?」——そんな不安を感じたことはありませんか?外来でもとても多いご相談です。
実は、膝の音にはいくつか種類があり、ただの“関節の泡がはじける音”で心配いらないものもあれば、体からの「そろそろ注意してね」というサインの場合もあります。
この記事では、膝の音のタイプや仕組み、年齢との関係、受診の目安、さらにご自宅でできるチェック方法やセルフケアまで、動画の内容をわかりやすくまとめました。まずは気になる音の正体を一緒に見ていきましょう♪
この記事で押さえてほしいポイント
- 高い音「ポキッ/パキッ」は、炭酸の泡がはじけるようなイメージ。関節液の気泡が弾けるだけなので、ほとんどの場合は心配いりません。
- 低い音「ギシギシ」「ゴリゴリ」「ジャリジャリ」は、タイヤがすり減ってきしむような状態。音が頻繁に出たり、痛みを伴うときは関節の摩耗(変形性膝関節症など)の可能性があります。
- 40代以降の女性はホルモン変化の影響もあり、軟骨の劣化が進みやすい時期。
「音の質が変わった」「前より重たい音になった」と感じたら、早めに整形外科で相談してください。 - 予防・改善のカギは「大腿四頭筋の筋力」「関節まわりの柔軟性」「体重コントロール」。
体重が1kg増えると膝には約3kg分の負担がかかるので、毎日の小さな積み重ねが将来の痛み予防につながります。
膝の“ポキポキ”の正体:主な3つの原因
音の起点は大きく3系統に分かれます。気泡由来/関節構造の問題/靭帯・腱のスナップです。まず全体像を俯瞰しましょう。
| 音の種類 | 機序・背景 | 特徴 | 危険度の目安 |
|---|---|---|---|
| ポキッ/パキッ(高め) | 関節液に生じた気泡が弾ける(圧変化による気体の溶出→破裂) | 一度鳴ると再充満まで15〜30分は鳴りにくい。痛みは伴わないことが多い。 | 基本は安全 |
| ギシギシ/ゴリゴリ(低め) | 軟骨の摩耗、半月板損傷など関節構造の問題 | 動かすたびに持続しやすい。痛みやこわばりを伴うと要注意。 | 要注意 |
| パチン(鋭い単発) | 靭帯・腱が骨を乗り越えるスナップ現象 | 姿勢・角度で出たり出なかったり。痛みがなければ多くは問題なし。 | 多くは安全(痛みがあれば受診) |
イメージとしては、炭酸飲料の「シュワッ」で生じる泡が弾ける瞬間のようなものが気泡音。指関節の“ポキポキ”と同じメカニズムで説明できます。

年齢・性別との関係:音の“質”が変わるタイミングに注意
年齢を重ねると、関節軟骨の含水量低下と弾力性低下が起きやすくなり、若い頃の「ポキッ」という軽い音が、次第に「ギシギシ」という摩擦音へ移行していくことがあります。おおよそ40歳以降で注意が必要で、とくに女性は閉経後のエストロゲン低下により軟骨の劣化が進みやすいとされます。
また、日本では推定2,500万人が変形性膝関節症に罹患しているといわれ、非常に身近な疾患です。「音の質が変わった」、階段での痛みや朝のこわばりなどが加わる場合は、早期に整形外科で評価を受けましょう。
“危険な音”の見分け方:セルフチェック表
音そのものだけでなく、頻度・痛み・随伴症状をセットで確認すると判断の精度が上がります。以下の表を目安にしてください(いずれか1項目でも「危険」に触れる場合は受診を)
| 判断ポイント | 安全サイン | 注意サイン | 危険サイン |
|---|---|---|---|
| 音の種類 | ポキッ/パキッ(高い) | ギシギシ/ミシミシ | ゴリゴリ/ジャリジャリ |
| 頻度 | 一度鳴ると15〜30分は鳴らない | 時々鳴る | ほぼ毎回鳴る |
| 痛み | なし | 軽い違和感 | 明確な痛み |
| その他の症状 | なし | 軽いこわばり | 腫れ・熱感・ロッキング(引っかかり) |
自宅での簡単チェックとしては、椅子座位の曲げ伸ばし/ゆっくりスクワット/階段の昇降の3動作で音と痛みを観察します(下表)。
| チェック項目 | 安全 | 注意 | 危険 |
|---|---|---|---|
| 椅子での曲げ伸ばし | ポキッと1回、痛みなし | ギシギシ音、軽い違和感 | ゴリゴリ音、痛みあり |
| スクワット動作 | 音なし/軽いポキッ | 摩擦音、軽いこわばり | 強い摩擦音、痛みで困難 |
| 階段昇降 | 問題なし | 軽い違和感 | 痛みで避けたくなる |

Q&A:よくある質問に専門医が回答
膝を鳴らすのは体に悪い?
- 関節液の気泡による音であれば、意図的に鳴らしても基本的に害はありません。ただし、無理なひねりは避け、自然に鳴る範囲にとどめましょう。
子供の膝もポキポキ鳴るのですが、大丈夫でしょうか?
- 成長過程で音が出ることは珍しくありません。痛みや運動制限がなければ経過観察でOK。ただしスポーツ中の痛みを伴うなら小児整形外科で評価を。
両膝とも鳴るのは片側と違う?
- 両側は全身的な要因(肥満・筋力低下・遺伝など)が関わる傾向。生活習慣の見直しを広く行いましょう。
サプリは効きますか?
- グルコサミンやコンドロイチンのエビデンスは限定的。まずは運動と体重管理を優先し、補助的に活用するなら医師と相談を。
音が急に「ギシギシ」に変わったら?
- 要注意サイン。レントゲンやMRIで構造的変化を確認しましょう。
セルフケアと予防法:今日からできる現実的アプローチ
1) 筋力強化——膝の安定化にもっとも寄与するのが「大腿四頭筋」。椅子に座って膝を伸ばし5秒キープ×10回を1日3セット。壁スクワットも有効(1日2セット、痛みの出ない範囲)。
2) 柔軟性の向上——太ももの前後・ふくらはぎを、体が温まった入浴後などに30秒×2〜3回。関節の可動域を保ち、摩擦感の軽減に役立ちます。
3) 体重管理と生活習慣——体重+1kgで歩行時の膝負荷はおおむね+3kg。長時間同姿勢を避け、1時間に一度は立ち上がって膝を動かす。階段は「上り健・下り患」を意識し、手すりを積極活用。
4) 温熱/冷却——慢性症状には温めが基本。急な腫れや熱感時は短時間の冷却も選択肢。5) 天気とのつき合い方——低気温・高湿度・気圧変動と痛み/こわばりの関連が報告あり。症状日誌に天気も併記すると診療の手がかりに。
動画でさらに詳しく解説
まとめ
- 「ポキッ/パキッ」は基本的に安全。「ギシギシ/ゴリゴリ/ジャリジャリ」は要注意。
- 痛み・腫れ・動きの制限(ロッキングなど)があれば受診を。
- 筋力強化・柔軟性・体重管理で、未来の痛みを予防できる。
音に過敏になりすぎる必要はありませんが、「音の質の変化」や「痛みの出現」には敏感でいてください。疑わしいときは、早めに整形外科へ。
参考文献
- Brennan-Olsen K, et al. Associations of weather parameters with osteoarthritis symptoms: Pain Medicine, 2023(低気温・高湿度・気圧変動と症状関連の報告)。:contentReference[oaicite:29]{index=29}
- Timmermans EJ, et al. The relationship between weather conditions and joint pain: Scandinavian Journal of Rheumatology, 2015. :contentReference[oaicite:30]{index=30}
- 変形性膝関節症の概説と国内有病推定(約2,500万人):動画台本内の説明より。:contentReference[oaicite:31]{index=31}
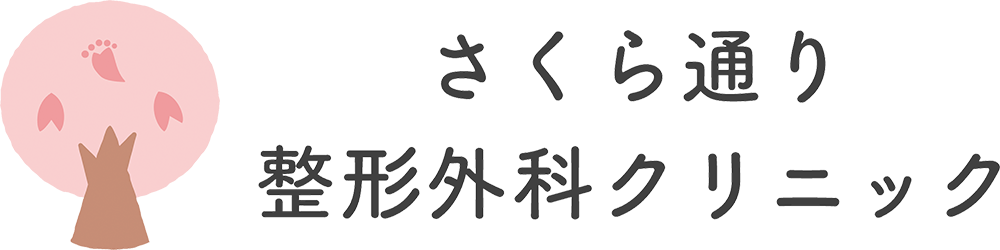


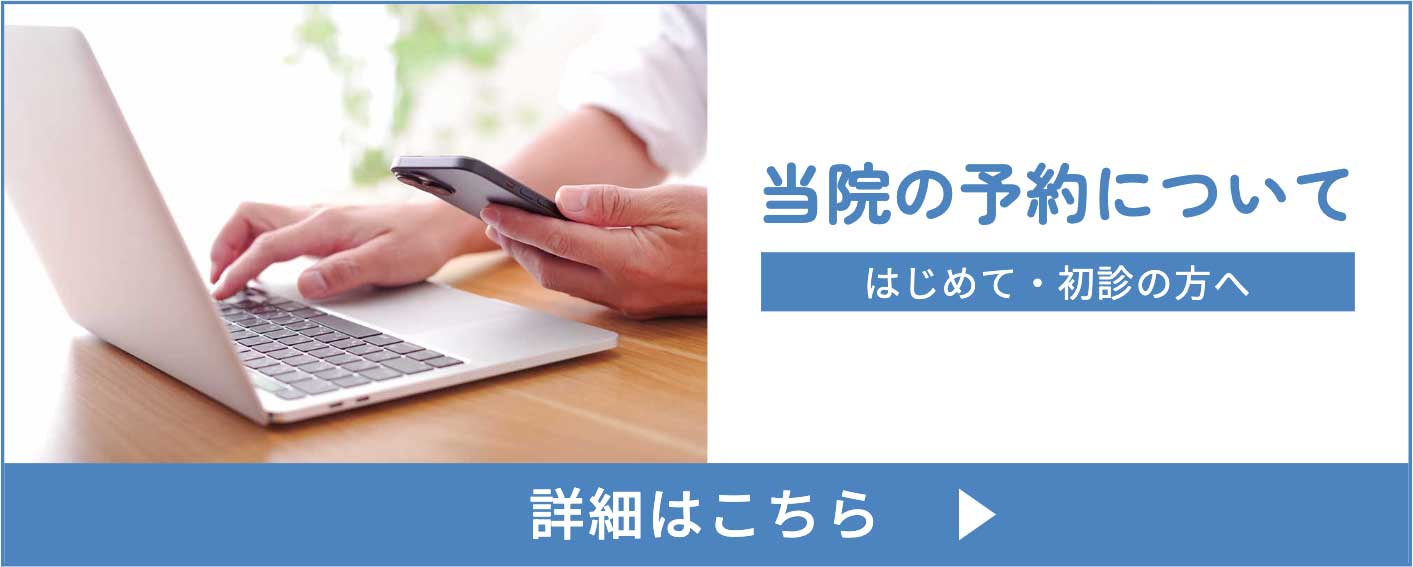
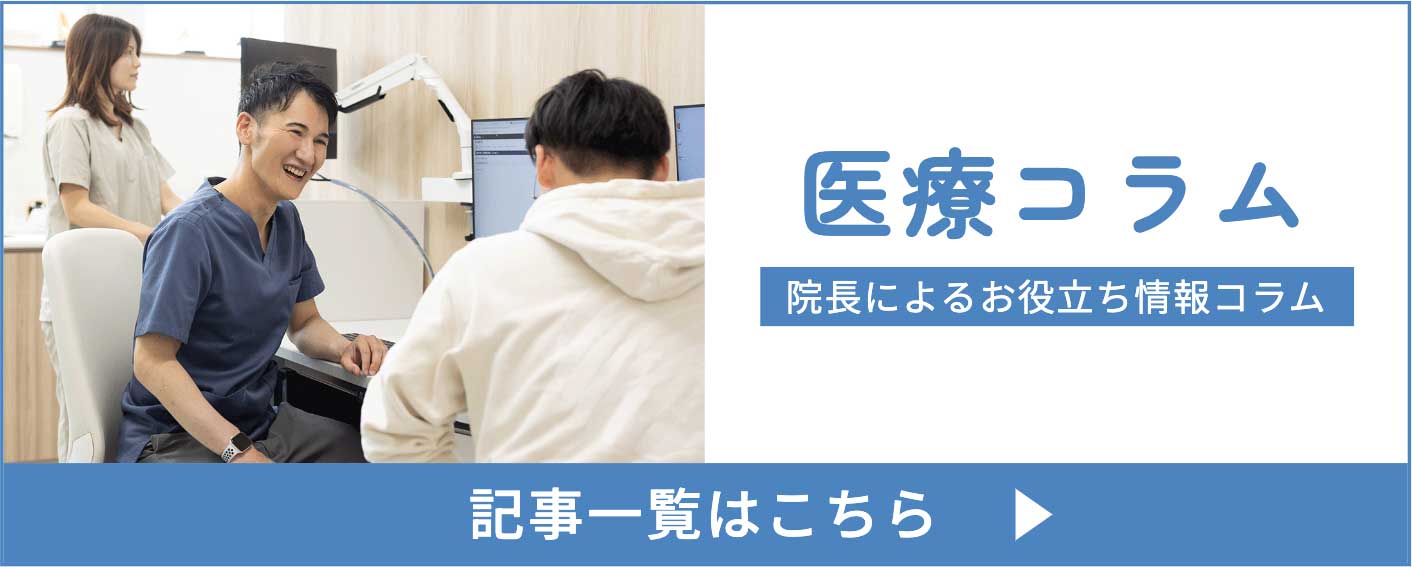



 公式Xはこちら
公式Xはこちら